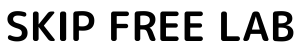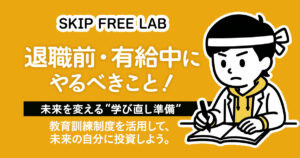会社を辞めて、フリーランスとしてスタートを切ったばかりの私。
これまで資産形成といえば「つみたてNISA」と「iDeCo」だったけれど、このタイミングで思い切って【小規模企業共済】に加入しました。
目的は、ずばり「借入」。
いざというときに使える“低金利の資金源”として、心強い選択肢になると考えたからです。
でも、それだけではありません。
これから事業を大きくしていきたい私にとって、資金を「守る」だけでなく、「攻め」にも使える余地がある——そんな可能性も感じたのです。
この記事では、小規模企業共済を選んだ理由や、借入を前提にどう活用していくつもりか、
個人事業主1年目の視点でリアルにまとめてみました。
- 小規模企業共済って“借入”にも使えるって本当?と気になっている人
- フリーランスとしての資金戦略を見直したい個人事業主さん
- iDeCoやNISAだけじゃ不安…もっと柔軟な選択肢を探している人
- 節税しつつ、いざというときに備えられる制度を知りたい人
- 「借金=悪」というイメージを少しずつ変えたいと感じている人
このブログ SKIP FREE LAB は、自由な働き方を模索しながら、発信と収入のバランスをゆるく実験している小さな実験室です。
ブログ収入で暮らしに余裕を(月5万目標)を目指しつつ、続ける工夫や働き方のヒントをまとめています。
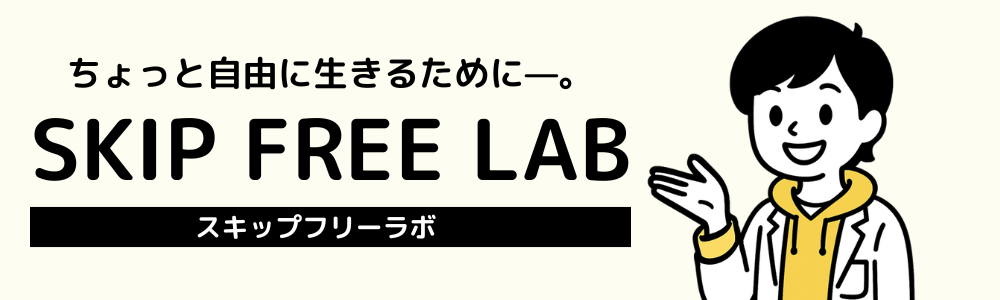
自由な働き方を目指すなら、まずは小さな一歩を確かに踏み出そう。
そもそも小規模企業共済って?

個人事業主のための“退職金制度”としても知られる、小規模企業共済。
加入対象や仕組みを正しく知ることで、活用の選択肢がぐっと広がります。
どんな制度?誰が加入できる?
小規模企業共済は、簡単に言うと「フリーランスや個人事業主が自分で積み立てる退職金制度」です。
加入対象は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主・会社役員など。私のような“ひとりフリーランス”でも、もちろん加入できます。
掛金は月1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で自由に設定でき、途中で増減することも可能。掛金は全額が「所得控除」の対象になるため、節税効果がかなり大きいのが魅力です。
私も正直、ここまでは「iDeCoと似てる?」くらいの認識でしたが…よく調べると、その特徴は思っていた以上にユニークでした。
掛金・節税効果・解約リスクの基本
小規模共済の大きなメリットは、なんといっても掛金全額が所得控除になること。
年間84万円まで控除できる仕組みは、節税を考える個人事業主にとって非常に強力です。
また、長期で積み立てれば将来の退職金として“共済金”を受け取ることができ、受取時の税制も優遇されています。
ただし注意点も。たとえば…
- 開始から短期間で解約すると「元本割れ」する可能性がある
- 原則として、事業を廃業・退職しない限り、満額の共済金は受け取れない
- 解約時の条件によっては「一括」「分割」など受け取り方に差が出る
つまり、“途中で気軽に使う貯金”としては向いていません。
でもこの制度には、もっとユニークな「裏ワザ」がありました…!
それが、私が今回もっとも注目した「貸付制度(借入)」という仕組みでした。
次の章では、その内容と魅力について詳しく紹介していきます!
なぜ私はiDeCoやNISAじゃなく、小規模共済を選んだのか

資産形成といえば「iDeCo」や「つみたてNISA」がよく話題に上がりますが、フリーランスになって改めて考え直したくなったのが“お金の置き場所”のこと。
私はこれまで両方を活用してきましたが、独立を機に「本当に今の自分に合った選択肢は何か?」を見つめ直しました。
iDeCoやNISAとどう違う?それぞれのメリット・デメリットを比較
資産形成といえば、つい「iDeCo」や「つみたてNISA」が思い浮かびます。
でも、いざフリーランスになると、「あれ、自分に今一番合う選択肢ってなんだろう?」と立ち止まりたくなる瞬間があります。
私自身、会社員のときはiDeCoとつみたてNISAをコツコツ続けてきました。
どちらも非課税メリットが魅力で、“将来への備え”としては文句なし。でも、いざ独立してみると、資金繰りの柔軟性とか、急な出費への備えとか、もっと現実的な視点で「使いやすさ」も重視したくなりました。
そこで候補に浮上したのが「小規模企業共済」。
個人事業主やフリーランス向けの制度として有名ですが、実はこの制度、単なる“退職金代わりの積立”だけじゃないんです。
なんと「事業資金を低金利で借りられる“貸付制度”」という裏の顔がある。
 《もえみそ》
《もえみそ》これ、思ってた以上に使えるのではないか!?
さらに言うと、小規模企業共済は、iDeCoよりも掛け金の増減が柔軟にできるし、万が一のときには“貸付”という選択肢もある。
もちろん年金の積立も大切。
でも、「80歳の100万円」と「今この瞬間の100万円」って、その価値はまるで違うはず。
若いうちに使えるお金をどう活かすか。それを考えたとき、私は“貯める”より“攻める”ほうに重心を置きたいと思いました。
だからこそ私には、小規模企業共済という選択肢がしっくりきたのかもしれません。
▼iDeCo、つみたてNISA、小規模共済の比較表
| 制度名 | 税制メリット | 資金の使いやすさ | 元本保証 | その他の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| iDeCo | 掛金が全額所得控除 運用益も非課税 |
原則60歳まで引き出し不可 | 運用次第で変動 | 加入条件あり。手数料がかかる |
| つみたてNISA | 運用益が非課税(最長20年間) | いつでも引き出しOK | 運用次第で変動 | 投資対象商品が限られている |
| 小規模共済 | 掛金が全額所得控除 共済金の受取も優遇 |
解約・貸付により引き出し可能 | 一応の保証あり | 共済貸付制度で低金利融資が受けられる点が特徴的 |
小規模企業共済を“借入目的”で見るとどうなの?

「小規模企業共済=退職金の積立制度」というイメージ、強いですよね。
でも私が注目したのは、もうひとつの顔――「低金利で借りられる貸付制度」でした。
この制度、実はあまり知られていないけど、うまく活用すればめちゃくちゃ心強い“資金源”になります。
どんな貸付があるの?
実はこの貸付制度、目的に応じていくつか種類が用意されています。以下のようなパターンがあります。
- 一般貸付(事業資金などに使える)
- 緊急経営安定貸付(売上減少などの際に)
- 傷病災害貸付(ケガや病気、災害など)
- 福祉対応貸付(介護や出産などに)
いずれも【年利1.5%前後(2025年時点)】という超低金利。
民間のカードローンや事業融資と比べたら、圧倒的に有利です。
どれくらい借りられるの?
目安としては、積立金の7〜9割程度まで借りられるとされています。
たとえば、月2万円を5年間積み立てたら…約120万円の積立があるとすると、最大100万円超を借りられる可能性も。
しかも、積立実績が“担保”になるので、審査も比較的スムーズです。
どんなときに使えるの?
たとえば…
- PCや撮影機材を買い替えたいとき
- 広告にまとまった資金を投じたいとき
- 外注やサービス購入で一気に加速したいとき
- キャッシュフローが一時的に苦しいとき
フリーランスは、「今このタイミングで資金があれば…!」って瞬間が会社員に比べて格段に多いのではないかと思います。
そんなとき、【自分の積立を担保に低金利で借りられる】貸付制度は、きっと心の安心材料になるはずです。
節税・借入・退職金控除の“3重取り”も夢じゃない!
小規模企業共済は、ただの「退職金の積立」ではありません。
うまく活用すれば、節税・借入・退職金控除の“三拍子”がそろった、フリーランスにとって最強の資金戦略になります。
- 退職金控除: 共済金を受け取る際、退職所得扱いで大幅に税負担を軽減
- 節税: 掛け金は全額が所得控除 → 所得税&住民税を軽減
- 借入: 積立を担保に、年1.5%前後という低金利で事業資金を確保できる
仮に、年利1.5%で借り入れた資金を、年3〜5%で運用できたら?
その運用益だけで、借り入れの利子分が実質帳消しになるケースもあり得ます。
もちろんリスクはありますが「貯めたお金を上手に回す」ことで、より柔軟で攻めの戦略を組めるのが、この制度の魅力かなと思っています。
積立 × 節税 × 低金利融資のトリプル活用。
小規模企業共済、これはもはや“ただの積立”じゃありません。賢く・現実的に動きたい個人事業主のための“資金戦略ツール”かもしれません。
加入前に知っておきたい“小規模企業共済”の注意点

小規模企業共済は、節税・退職金・低金利の借入と、メリットが豊富な制度です。
でも実際に加入してみて、「事前にここは知っておくべきだったかも…!」と思った点もいくつかありました。
特に気をつけたいのが、「掛金の減額」や「短期での解約」にまつわる仕組み。
たとえば、掛金を減額した場合、その減額分は運用対象から外れてしまい、将来受け取れる共済金にも影響が出ます。
しかも、その分をあとから再増額しても、失った運用期間は取り戻せないという仕様。
(公式サイトのQ&Aにも明記されています → 中小機構Q&Aリンク)
このような理由から、加入前には“どのくらいの金額を、どれくらいの期間続けられそうか”を、ざっくりでもいいので見通しておくことが大事だと感じました。
ここからは、実際に私が加入前に知っておきたかったポイントを3つに絞ってお伝えしていきます!
掛金の減額や停止には注意が必要
毎月の掛金は500円単位で設定できますが、途中で減額してしまうと、その減額分は運用対象から外れてしまいます。
また、一度減額したあとに増額を申請しても、元に戻せないケースもあるとのこと(上限あり・要審査)。
「しばらく収入が不安定だから…」と安易に下げてしまうと、将来の共済金が目減りするリスクもあるので要注意です。
元本割れのリスクもゼロではない
共済は“長く積み立てる”前提の制度です。
加入から短期間で解約すると、元本割れ(支払った掛金より少ない金額しか戻らない)になる可能性も。
満期や65歳以降の任意解約、廃業・死亡など正当な理由があれば元本割れは基本的に防げますが、やむを得ず早期解約した場合は痛手になることもあります。
原則として、共済金は“老後資金”。すぐには使えない
貸付制度があるとはいえ、積み立てた共済金自体は、基本的には“老後資金”として想定された制度。
つまり、使いたいときに自由に取り崩すことはできません。
特に、積み立ててすぐに「まとまったお金が欲しい」となっても、引き出せない可能性があるので注意が必要です。
※退職・廃業・死亡などがないと「共済金」として受け取れないケースがほとんどです。
最初の掛け金は月2万円。でも少し不安…
小規模企業共済に申し込むとき、私は「月2万円」でスタートすることにしました。
正直、もっと高くしたほうが節税効果はあるし、将来の積立額も増えるってわかってはいたけど…。
でも、独立してすぐのこのタイミングで、仕事の量もまだ安定してるとは言えないし、収入がどう推移していくかも未知数。なので私は、「まずはムリなく続けられる金額でスタートしよう」と決めました。
あとから「増額できないかもしれない」っていう話を知って、少しだけ焦ったけれど、
よくよく調べてみると、最初に決めた金額で20年しっかり積み立てていければ、それでも十分意味はある。
大きな掛け金でプレッシャーになるより、小さくてもコツコツ継続できるほうが絶対に強い。
 《もえみそ》
《もえみそ》とりあえず2万円!ゆくゆくは7万マックスで掛けれるように頑張る!
でもそれは、“いまの私”が考えた、“これからの私”のためのできる限りの資金戦略です!
【まとめ】攻める個人事業主にこそ、小規模企業共済はアリかも!

小規模企業共済といえば、「退職金の積立制度」というイメージが定番。
でも、本当の魅力は“使い方次第”で広がる柔軟性にあります。
たとえば…
- 掛け金は全額が所得控除 → 節税効果◎
- 解約や貸付によって、柔軟に資金が引き出せる
- 万が一に備えながら、低金利で借りられる“裏ワザ”制度も完備!
特にフリーランスや個人事業主にとっては、「今この瞬間に動けるお金がある」ことが、成長スピードに直結します。
もちろん、メリットばかりではありません。
20年未満の短期解約で元本割れのリスクがあったり、掛け金の再増額が難しかったりと、注意点もきちんと押さえておく必要があります。
でもだからこそ――
✅ 節税だけじゃない!
✅ 資金調達の選択肢としてもアリ!
✅ “守り”だけじゃなく“攻め”にも使える!
そんな自分なりの資金戦略を描ける制度だと、私は感じています。
これから独立する人も、すでにフリーランスとして動いている人も。
「お金の使い方」に“もう一歩踏み込んだ視点”を持つことで、次のアクションがもっと現実的に見えてくるかもしれません。
あなたにとって、今いちばん合う選択肢はなんですか??
 《もえみそ》
《もえみそ》この記事が、フリーランス準備を進める誰かの、不安を少しでも軽くできたらうれしいです🌱
他の「フリーランス準備」の記事も、少しずつ更新していきます!
- 退職後のやることリスト7選|保険・年金・税金・開業の完全ガイド
👉 退職後すぐにやるべき手続きをまとめた完全ガイド。 - フリーランス1年目に向けて今やっておきたい5つの準備と心構え
👉 事前に知っておきたい準備やマインドセットをまとめました。 - 収入ゼロでスタートしない!会社員のうちにやるべきフリーランス準備
👉 スキル・実績・お金の準備について具体的に解説しています。