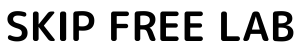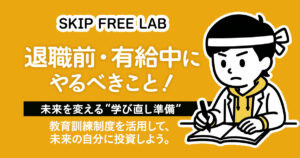《もえみそ》
《もえみそ》退職したら、iDeCoってどうなるんだろう?
最近ふとそんな疑問が浮かびました。
個人で始めたiDeCoをこのまま続けられるのか、手続きは必要なのか、そもそもこのままで大丈夫なのか——
調べてみると、「やめられない」「引き出せない」「企業型と個人型がある」など、意外とややこしいルールがいろいろと…!
私自身も「今のうちに知っておいて本当によかった」と思ったので、この記事にまとめておくことにしました。
iDeCoに加入している会社員の方や、これからフリーランスを目指す方にとって、
この記事がちょっとした道しるべになればうれしいです。
- iDeCoに加入していて、これから退職・フリーランスになる予定の会社員の方
- 「iDeCoって退職後どうなるの?」「手続きって必要なの?」と不安を感じている方
- 企業型DCとiDeCoの違いや、継続・種別変更についてやさしく知りたい方
- 小規模企業共済との違いや、どちらを優先するか悩んでいる方
📌 会社を辞める前に、こんな記事も読まれています
▼ フリーランスに向いているか不安な人へ
👉 フリーランスに向いている人の特徴とは?5つの視点で“適性”をセルフチェック!
▼ 退職に向けて準備中の人へ
👉 収入ゼロでスタートしない!会社員のうちにやるべきフリーランス準備
▼ フリーランス1年目を安心して迎えたい人へ
👉 フリーランス1年目に向けて今やっておきたい5つの準備と心構え
▼ 有給中に“学び始め”たい人へ
👉 退職前・有給中にやるべきこと|“学び始め”で得られた3つのメリット
▼ 退職後の手当制度が気になる人へ
👉 退職後の失業手当“受給期間延長”制度とは?私が申請しなかった理由
このブログ SKIP FREE LAB は、自由な働き方を模索しながら、発信と収入のバランスをゆるく実験している小さな実験室です。
ブログ収入で暮らしに余裕を(月5万目標)を目指しつつ、続ける工夫や働き方のヒントをまとめています。
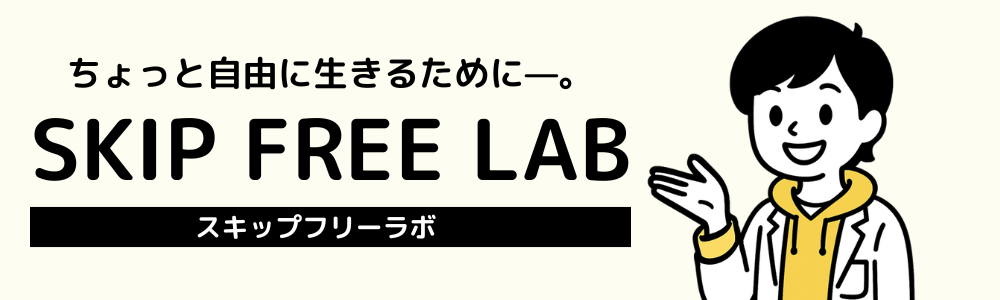
自由な働き方を目指すなら、まずは小さな一歩を確かに踏み出そう。
退職するとiDeCoはどうなる?【まずはここから整理】

会社員のiDeCo、退職後はどうなる?
退職しても、iDeCoや企業型DCは自動的に解約されたり、脱退できたりするわけではありません。
引き続き制度を活用するには、「継続」や「移換」「種別変更」など、必要な手続きを自分で行う必要があります。
iDeCoは、自分で掛金を出して運用する私的年金制度。一方の企業型DCは、企業が掛金を出し、従業員が運用する確定拠出年金制度です。
どちらも原則として60歳までは引き出すことができません。
私も「このまま何もしなくても、きっと勝手に切り替わるのかな?」と思っていたのですが、
実際は制度上、明確な意思表示と手続きが求められることを知り、早めに対応することにしました。
拠出停止もできる?注意したい制度上のリスク
iDeCoを継続するにしても、「続け方」にはいくつかの選択肢があります。
そのひとつが、「拠出をいったんストップする(=掛け金をゼロにする)」という方法です。
ただし注意点として、
- 拠出を止めても口座管理手数料がかかる
- 継続の意思を示さないと「自動的に加入資格喪失扱い」になることもある
といった点があります。
自分がどのタイプで加入していて、今後どうするか?を自分で選んで手続きする必要があるというのが、退職後のiDeCo最大のポイントです。
掛け金の減額は可能?見直しのタイミングと注意点
拠出を完全に止めるほどではないけれど、もう少し負担を軽くしたい——
そんなときに検討できるのが「掛け金の減額」です。
iDeCoの掛け金は、資金繰りが厳しいときなど、状況に応じて見直すことができます。
私も今後の収入の変動を見越して、掛け金を減額することにしました。
なお、掛け金の変更は年に1回までなので、タイミングを考えたうえで計画的に判断することが大切です。
企業型DCからiDeCoへ|移換の流れと注意点

企業型DCとは?退職後はどうなる?
「企業型DC(確定拠出年金)」とは、企業が掛金を出し、従業員が自分で運用する年金制度のことです。
退職金制度の一部として導入している企業も多く、福利厚生のひとつとして知られています。
ただし、企業型DCは在職中であることが加入条件。
つまり、退職と同時にこの制度を継続できなくなってしまいます。
このとき重要なのが、企業型DCをどう扱うかを「自分で選ばないといけない」という点。
何もしないまま放置すると、“自動移換”というリスクのある状態になってしまうんです。
iDeCoに移換するには?手続きの流れ
退職後、企業型DCの資産を引き続き運用したい場合、
「個人型iDeCoに資産を移換する」という手続きを行う必要があります。
この移換は自動で行われるものではなく、自分で書類を準備し、期限内に手続きを進める必要があります。
大まかな流れは以下のとおり:
- iDeCo口座を開設する(証券会社・銀行などで申請)
- 「企業型DC→個人型iDeCo」への移換書類を提出
- 企業側からの情報提供や証明書を求められることもあり
申請から完了まで1〜2ヶ月以上かかる場合もあるので、早めの行動がカギです。
放置リスクと、早めの行動が大切な理由
もし何もしないまま放置すると、企業型DCの資産は*「自動移換」されてしまいます。
これは、資産が運用できない元本保証型商品に移され、運用停止状態になること。
さらに、毎月の手数料(口座維持費)だけが引かれ続ける状態になってしまい、
せっかく積み立ててきた年金資産が、少しずつ目減りしていくことにもつながります。
だからこそ、退職前〜直後のタイミングで、
「企業型DC→iDeCoへの移換」を自分の意思でスムーズに行うことが本当に大切です。
私の場合は「個人型iDeCo→継続」だった

退職後、個人型としてそのまま継続する方法
私はもともと「個人型iDeCo」に加入していたため、退職後もそのまま続けることができます。
ただし、会社員時代は「第2号被保険者」だったのに対し、フリーランスになると「第1号被保険者」に種別が変わります。
そのため、iDeCoを続けるには「加入者種別変更届」を提出する必要がありました。
提出先はiDeCoを申し込んだ金融機関で、Webや郵送で書類を請求 → 記入 → 郵送で提出という流れです。
ちなみにこの「第1号被保険者」になると、iDeCoの掛け金上限が月6.8万円まで増えます(条件により異なります)。
そのぶん節税効果も大きくなりますが、毎月のキャッシュフローも考慮して、私は上限まで積み立てず、少額に減額して継続することにしました。
種別変更の手続きと実際に調べてわかったこと
この手続き、正直「もっと簡単にできないの…?」と思うくらいにややこしい…。
わかりづらい専門用語が多かったり、「そもそも自分がどの種別なのかよくわからない」という人も多いはずです。
でも実際にやってみてわかったのは、“一度ちゃんと理解してしまえば怖くない”ということ。
ネットで調べながら少しずつ進めれば、時間はかかってもちゃんと完了できます!
私が掛け金を減らした理由|小規模企業共済という選択肢
そしてもうひとつ、個人型iDeCoを継続する中で考えたのが「掛け金の見直し」でした。
私は今、掛け金を減額する手続きを進めています。
理由は、小規模企業共済の方が“いざというときにお金を借りられる”制度だから。
iDeCoは老後資金に特化していて引き出せない一方、小規模企業共済は事業資金や生活資金として活用できる「貸付制度」があります。
フリーランスは予期せぬ出費も多いので、「いざというときに使える備え」として、柔軟性の高い共済制度を優先する判断をしました。
まとめ|退職前に確認しておきたい3つのこと

① iDeCoは「やめられない」制度。だからこそ、継続方法をチェック!
iDeCoは基本的に60歳まで引き出せない「積立専用」の制度。
退職しても自動で止まったり、脱退できるわけではありません。
そのまま続けるのか、拠出を止めるのか、ちゃんと手続きする必要があります。
私自身は、退職の約2ヶ月前に証券会社に書類請求をしましたが、変更完了までに1ヶ月〜1.5ヶ月以上かかる場合があると記載がありました。
書類の取り寄せ、記入、郵送…と、想像以上に時間がかかるので、「いつかやればいい」ではなく、「退職前に調べておく」ことが本当に大切です。
② 自分が企業型DCなのか、個人型iDeCoなのかを確認しよう
同じ“確定拠出年金”でも、企業型と個人型ではルールや手続きが全然違います。
自分がどちらに入っているのか?をまず確認するところからスタートです。
企業型の人は移換の手続きが必要ですし、個人型の人も種別変更が必要です。
「放置するとどうなるのか?」も含めて、早めの確認がおすすめです!
③ すべてをiDeCoに頼らない選択肢もある(共済制度など)
私自身は、iDeCoの掛け金を減らしつつ、小規模企業共済を活用することにしました。
理由は「いざというときに使える制度」を優先したいから。
どの制度も一長一短があるからこそ、「自分のライフスタイルに合った備え方」を見つけておくことが、これからのフリーランス生活を安心してスタートするための鍵になると思います。
(※小規模企業共済については、別の記事で詳しくまとめる予定です!)
 《もえみそ》
《もえみそ》この記事が、フリーランス準備を進める誰かの、不安を少しでも軽くできたらうれしいです🌱
他の「フリーランス準備」の記事も、少しずつ更新していきます!